
株式会社e‑Gridによる特別講義を開催
2025.11.25
2025年11月6日、神戸市立工業高等専門学校で株式会社e‑Grid(以下、イーグリッド)による特別講義が行われました。
イーグリッドは島根県出雲市に本社を置くIT企業で、2022年には神戸にも進出し、事業を拡大しています。
将来や進路について考え始めている電子工学科3年生たちは、普段なかなか聞くことのできない現場の生の声に静かに耳を傾けました。
ーー ローカルからグローバルへ。地方発ITが拓く新時代
講義ではまず、代表取締役CEOの小村淳浩さんが登壇し、「IT×Xでより良い社会を創造する」をテーマに会社設立の経緯や現在の事業などについて語りました。
小村さんは大学時代に読んだ自動運転の記事をきっかけにモビリティ分野に関心を持ち、大手電機メーカーで約10年間、SE・コンサルタントとして従事。地元の出雲市にUターン後、2010年にイーグリッドを創業しました。
現在はソフトウェア開発を中核に、MaaS(モビリティをサービスとして提供する仕組み)、ITコンサルティング、デジタルマーケティングなど、さまざまな事業を展開。自社プロダクト開発にも注力し、AIを活用した製品開発を進める一方で、BPO(企業の事務やデータ業務等を専門会社に任せる仕組み)といったアナログな仕事にも積極的に取り組んでいます。小村さんはその理由について「AIを適切に導入するには、現場の課題を高い解像度で把握することが不可欠」と説明。現場に深く入り込む「アウトソーシング」とAIを駆使した「プロダクト開発」の両軸で課題に向き合い、実務に根ざした価値創出を重視しています。
また、自社を「主役ではなく、縁の下の力持ち」と表現し、重要なのは「自動車・情報通信・防災・芸能など、多様な産業が持つ価値とイーグリッドが持つ価値を掛け合わせ、新たな価値を創造することだ」と言います。
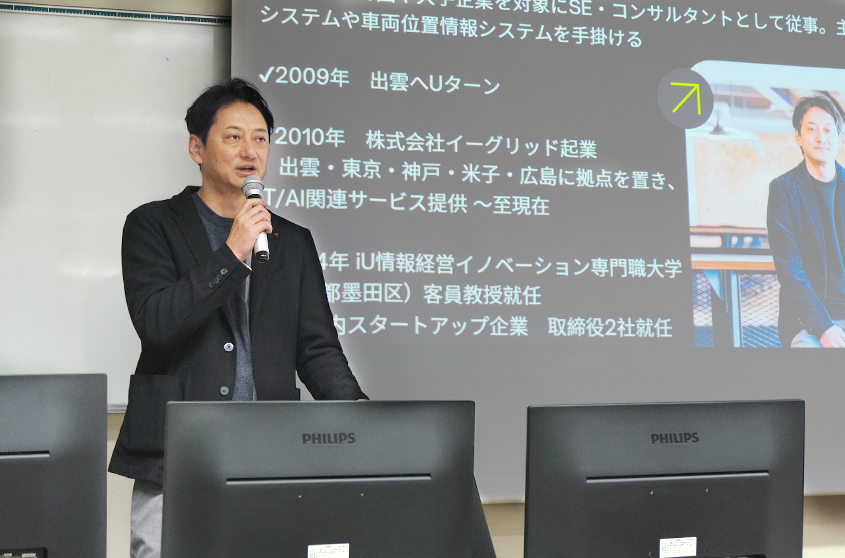
ーー 生成AIの台頭と「専門性」の価値
近年、IT分野の中核を担う技術として急速に存在感を強めているのが生成AIです。その進化は目覚ましく、「プログラマーの仕事がAIに代替されるのでは」と危惧する声もあります。しかし小村さんは、「高い専門性があれば心配はいらない」と断言します。
「AIの普及に伴いサイバー攻撃のリスクが高まり、セキュリティの重要性がさらに増している。また、日本は生産技術やセンサー技術では世界トップクラスの力を持っている。今後はこうした領域にプログラマーやIT人材が関わっていく可能性が高い。自分の専門技術と他分野の技術者の知見を掛け合わせることで、新しいソリューションやイノベーションを生み出す姿勢を大切にしてほしい」と学生たちに語りかけました。
ーー 国境を超えて社会課題と向き合う
次に小村さんは、現在注力しているMaaS事業の一つとして、タイ・バンコクで進めている脱炭素化プロジェクト(経済産業省関連事業)について紹介しました。
バイク利用が非常に多いバンコクでは、交通渋滞や大気汚染が深刻化しており、タイ政府はその対策として電動バイクの普及を推進しています。
こうした状況を受け、イーグリッドはAIやデータサイエンスを活用してバイクタクシーの運転傾向を細かく分析。電力消費を抑えるためのエコドライブ診断を行い、電動バイクのエネルギー効率向上とCO₂削減に取り組んでいます。また、運行データを可視化し、行政や企業に役立つ情報として提供することも本事業の重要な目的としています。
来年には現地での実証実験も予定されており、国内外で活躍の場を広げる同社の取り組みに、学生たちは関心を深めました。
ーー 未来の技術者・起業家に必要な思考とは
技術者としてだけでなく、将来の起業家候補としても成長する学生たちに向け、小村さんは強調します。「技術を高めることは大事だが、それだけでは社会の役に立てない。誰のどんな課題を解決するのか、提供するサービスが価値を生むか、そして事業に拡張の兆しが見えるかどうかを意識しながら技術を磨くことが重要だ」
また、大学で研究を続ける場合も、社会課題を理解しビジネスとの接点を見つけ、「自分の制作したものがマーケットに合っているか、短いサイクルで試作・検証・改善を繰り返しながら前に進めていくことが必要である」と述べました。
ーー 幅広い経験が育んだ課題解決力
続いて、取締役CTOの永見純也さんが登壇し、「エンジニアリングとAIで広がる未来」をテーマに、技術の現場活用やAI時代における進化、エンジニアリングの本質などについて講義を行いました。
永見さんはコールセンター業界からIT業界へ転身した異色の経歴の持ち主です。前職ではチームリーダーを経てシステム担当に抜擢され、独学でプログラミングを習得したことをきっかけにエンジニアとしてのキャリアを歩み始めました。
コールセンター時代はさまざまな業務を任され、建物管理や除雪作業まで経験。「現場での実務を通して、課題解決の重要性や苦手分野にも挑戦してスキルを磨く大切さを学んだ」と言います。

ーー 現場を知ることがシステム開発の第一歩
同社では社員の約8割にあたる100人がエンジニアとして活躍し、フロントエンド(画面)からバックエンド(サーバー)、クラウドまで一貫して開発できる体制を構築。シニアと若手が連携し、安定して高品質なサービスを提供しています。
自社のシステム開発の流れについて説明する中で永見さんは、「業務全体を理解することが良いシステムをつくる第一歩」と提言。
さらに「現場の課題を見極め、どこまでをシステム化するべきか、そしてどんな人が使うのかを明確に設計することが重要だ」と続け、「すべてをシステム化しても実際に使われなければ意味がない。だからこそ業務フローの全体像を把握し、効果が出るポイントを見極めることが欠かせない」と指摘しました。
ーー AIは脅威ではなく、生産性向上のパートナー
同社では2024年にAIプロダクト開発チームを立ち上げ、AIを活用した新サービスの創出を推進しています。しかし、AIの生成物は不完全な部分も多く、人間によるレビューと検証が欠かせません。また、熟練エンジニアはAI活用によって生産性が約3倍に向上する一方で、若手は十分な効果を得にくいという傾向も見られるのだそうです。
永見さんは「AIは仕事を奪うものではなく、理解して正しく使いこなすことで価値を生む」と明言し、「AIを使いこなすには、まず基礎的な技術力をしっかり身につけることが不可欠」と実感を込めました。
そして、エンジニアリングの本質を「課題解決の仕組みをつくること」とし、AIは「生産性を高めるパートナー」と説明。どの技術をどの場面で使うべきか判断する思考力に加え、チームで価値を生み出す力や、技術変化に対応するための継続的な学習の重要性も示しました。
最後に永見さんは学生たちに向けて、「技術の変化を楽しみながら学び、より良い未来を創造してほしい」とエールを送りました。
ーー 学生からの質問
質疑応答では学生たちが次々に手を挙げ、活発な意見交換が行われました。
「新しい技術が次々に出てくるが、どうやって学んでいるのか?」との問いに対し、永見さんは、「社内勉強会や地域の同業者コミュニティでの情報交換を通し、日々学び続けている。技術者は新しい技術を得ることに喜びを感じる人も多い。学び自体を楽しむ姿勢が大切だ」と答えました。
また、タイで事業を行う理由について問われた小村さんは、「当社のビジョンである『技術で社会課題を解決する』に基づき、国内外を問わず幅広く仕事に取り組むのが私たちのスタイル。海外プロジェクトを通して現地の文化や商習慣を学び、メンバーの成長と会社の発展につながっている」と伝えました。

ーー 講義を受けて〜学生たちの感想
小村さんと永見さんの話に熱心に聞き入った学生たちからは、前向きな声が多く聞かれました。
「国内外で幅広い事業を展開している点が印象的だった。ソフトウェア開発をさまざまな領域と組み合わせ、新たな価値を生み出している同社に大きな魅力を感じる。将来はIT分野も進路の選択肢に加えたいと思う」
「プログラミング関連の仕事を目指している私にとって、会社でのシステム開発の流れや体制を具体的に知ることができたのは大きな収穫だった。将来は私もプログラミングで社会課題を解決できるよう、新たな技術を身につけていきたい」
電子工学科3年生にとって企業の方から直接話を聞くのは初めての経験で、自分の将来や現在の学びについて改めて考える貴重な時間となったようです。
ーー 講義を通して、小村さんと永見さんが感じたこと
講義を終えたお二人は、「優秀な学生さんばかりで、熱心に話を聞いてくれて嬉しかった」(小村さん)、「当社について興味を持ってもらえたようでよかった」(永見さん)と、ほっとした表情を見せました。
さらに小村さんは、講義で伝えきれなかった思いを次のように語りました。
「創業時に掲げた当社のキーワードは“ヘンタイ”。他社からヘンだと思われるくらい、常識にとらわれない挑戦をし続けようという意味だ。誰の役に立たなくても、時には自分がおもしろいと思うことに集中することで、技術者たちの挑戦するマインドを育てている。理系の学びの先には、研究者・技術者・起業など将来の選択肢が多様に広がっている。もしレールから外れても、再び自分で学ぶことを決め、柔軟に挑戦してほしい」
同社は、都市機能を備えつつ中山間地にも近い神戸に魅力を感じ、研究や実証実験の拠点として神戸オフィスを開設。今後は神戸での人材確保にも力を注ぐ予定で、「今日、聴講してくれた学生さんが、将来的にイーグリッドで活躍してくれたら嬉しい」と期待を膨らませました。

<株式会社 e‑Grid>
設立 2010年
代表者 代表取締役 CEO 小村淳浩
事業内容 ソフトウェア受託開発、デジタルマーケティング、ITコンサルティング、自社プロダクト開発、AI・MaaS・GIS開発、ラボ型開発、研究実証
所在地
■本社 島根県出雲市常松町526
■神戸オフィス 兵庫県神戸市中央区八幡通3-1-14 サンシポートビル6階
■東京オフィス、出雲開発センター、米子オフィス、広島オフィス
